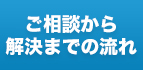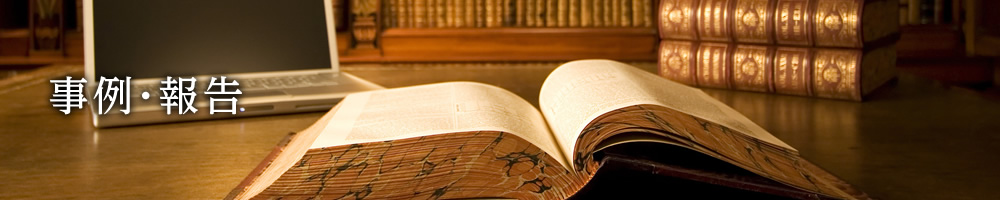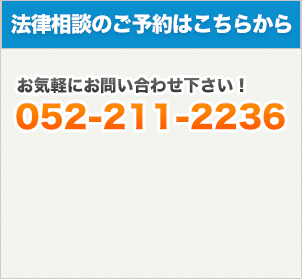事例・報告
公正証書遺言を勧められましたがメリットは?
遺言書は自分で作成する「自筆証書遺言」もありますが、公証役場で作ることも出来ます。これを「公正証書遺言」と言います。
メリットとしては、①公証人が作成しますので、後に偽造・変造と揉めることはないこと、②遺言の内容が明確になること、③自筆証書遺言の場合の家庭裁判所での「検認手続き」が不要であること、④遺言書を公証役場が保管をしてくれること、⑤文字がうまく書けなくても作成出来ること、があります。また、公証役場に行って作成することが原則ですが、自宅や介護施設に公証人が出向くことも出来ます。
一方、デメリットとしては、①遺言書完成までに内容確定のための公証役場とのやりとりが必要であること、②作成費用がかかること(遺産の額や受遺者の数等により計算されますが、数万円程度が多い)があります。
なお、遺言書の作成を弁護士に依頼をすれば、弁護士費用はかかりますが、公証役場との連絡や遺言書の内容の確定のためのやりとり、公証役場に行く日程の設定等、弁護士がやってくれます。これらのメリットデメリットを考えて決められるとよいでしょう。
遺留分侵害額請求権とは
遺言状の執行や生前贈与で、相続分がない場合でも、配偶者や子(子がいないときは親)など、兄弟姉妹を除く法定相続人は、遺留分侵害額請求権として、相続財産の一定割合の金銭を請求する権利を持ちます。

これは、被相続人の遺産の中に、夫婦や親子の潜在的持ち分が混入していることや、夫婦は、本来互いに協力して生活すべきとされていること、親子は扶養の義務があることなどから、認められている権利です。
遺留分を算定するための財産は、以下のとおりです。
被相続人が相続開始の時において有した財産の価格+被相続人の贈与財産の価格
-被相続人の債務の全額
遺留分は、上記の価格に、各自の相続分と、親等の直系尊属のみが相続人である場合は、3分の1、配偶者や子など、それ以外の相続人は2分の1を乗じた額となります。
この請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは時効によって消滅してしまいます。
相続開始から10年を開始した時も消滅します。
詳しいことは、弁護士にお尋ねください。
相続放棄をしても、不動産の保存義務があるの?
「相続放棄をしても実家の管理をし続けなければならないのでしょうか?」というような相続放棄後の不動産の保存義務があるかどうかについて、ご相談を受けることがよくあります。
この問題については、民法が改正され、
「民法940条1項(相続の放棄をした者による管理)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」
と定められています。
つまり、「現に占有しているとき」に限って、「財産を保存」する義務があるとなっていますから、相続放棄をされた方がその不動産を占有していなければ、保存義務がないことになります。
なお、その不動産を占有されている方は、これまでと変わらず、他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでは保存義務があることになります。
民法改正前は、インターネットの情報などを読まれ、相続放棄をした後、不動産の管理をし続けなければならないのかとご不安を口にされる方もいましたが、民法改正によりこの点が明らかになりましたのでお知らせします。
相続登記の義務化
相続登記の義務化(令和6年4月1日から)
令和6年4月1日から、相続により取得した不動産について登記が義務化されました。その主な内容は、以下のとおりです。
1 義務の内容
相続により自分が不動産を取得したことを知った日から3年が過ぎても、正当な理由なく登記の申請をしていない場合、法務局から登記を「催告」されます。その催告にも応じず登記をしない場合、10万円以下の過料が課されます。
2 過去に相続した不動産にも適用
相続登記の義務化は、令和6年4月1日よりも前に相続したけれど相続登記はまだ行っていない不動産にも適用されます。
ただし、このような場合、令和9年3月末日まで猶予期間がありますので、それまでに相続登記を行えば、過料が課されることはありません。
3 相続で揉めていて登記ができない場合
通常の相続登記とは別に、相続が始まったことと自分が相続人であることの届出をして登記することもできます(相続人申告登記)。他の相続人の同意は必要なく、自分1人で手続きができます。
自分は相続登記をしたいけれど、他の相続人との遺産分割協議が揉めているため、相続登記ができないという場合もあるでしょう。このような場合でも、この相続人申告登記を3年以内に行えば、相続登記の義務が履行されたことになり、過料が課されることはありません。
4 DVの被害者など住所を知られたくない場合
相続登記をすると、不動産登記には、所有者となった人の氏名だけでなく住所も記載されます。この情報は公開ですので、誰でも見ることができます。しかし、DVの被害者など自分の住所を知られたくないという人もいるでしょう。
このような場合、不動産登記の際に申し出れば、現住所の代わりに当事者と連絡がとれる弁護士事務所や被害者支援団体、法務局の所在地を住所として記載できるようになりました。
ご不明な点などありましたら、当事務所まで遠慮なくお問い合わせください。
遺言能力とは
遺言は,自分の意思に沿って遺産を分けたい,将来,遺産を巡って相続人が揉めるのを避けたい,などの希望を叶えることができるなど,多くのメリットがあります。
もっとも,遺言について,遺言者の死後,その有効性を巡って相続人間で紛争になることがあり,その場合は却って紛争が発生する可能性もあります。
そこで,有効な遺言を作成するためにはどのようにしたら良いでしょうか。
実務上最も多く争われるのは,「遺言能力の有無」です。遺言能力とは,「遺言内容及びその法律効果を理解判断するのに必要な能力」を指します。要するに、遺言の内容を十分に理解できるだけの判断能力のことになります。
典型的には認知症を抱える高齢者の遺言で「遺言能力」が問題になりやすいです。
過去の裁判例では,遺言の内容,遺言者の年齢,病状を含む心身の状況及び健康状態とその推移,発病時と遺言時の時間的間隔,遺言時とその前後の言動及び健康状態,日頃の遺言についての意向,遺言者の受遺者の関係,前の遺言の有無,前の遺言を変更する動機・事情の有無等遺言者の状況を総合的に見て判断するとされています。
このように様々な考慮要素もあるため,「遺言能力」の有無の判断は専門家でも意見が分かれることも多いです。
その中でも一番重要な要素は,やはり遺言者の判断能力です。そして,その判断能力は,長谷川式スケールやMMSEスケール等の認知症のテストの点数で数値化されます。
非常に大ざっぱに申しますと,長谷川式スケールのテストの結果が
20点以上→有効である可能性大
10点台→ケースバイケース
10点未満→無効である可能性大
 という理解がされています。ただし,上記の通り遺言能力の有無は,様々な考慮要素を総合的に考慮して判断されるので,長谷川式スケール等の結果は目安に過ぎず,テストの結果だけで一律に判断することはできません。それでも,実務上はこの点数が非常に重要な考慮要素であることは確かです。
という理解がされています。ただし,上記の通り遺言能力の有無は,様々な考慮要素を総合的に考慮して判断されるので,長谷川式スケール等の結果は目安に過ぎず,テストの結果だけで一律に判断することはできません。それでも,実務上はこの点数が非常に重要な考慮要素であることは確かです。
これらの遺言能力の判断基準を踏まえた上,有効な遺言を作成するためには,遺言作成の先立ち,長谷川式スケール等のテストを実施したり,医師の診断書を書いて頂く,遺言内容の聞き取りをする際に動画撮影をするなどの証拠化の作業が重要です。
また,公正証書遺言の方法で作成した方が,公証人のチェックが入るため,自筆証書遺言よりも遺言能力が認められやすいと言えます。
以上のように,遺言能力の観点からも有効かつ,それを証拠化した遺言を作成するためにも,遺言作成の際には予め弁護士に相談しておくことをお勧めします。
遺言書作成の必要性

遺言書を作成するメリットは、①遺産の分け方について自分の意思を反映させることができること、②将来の相続トラブルを回避しやすいことになります。
そのため、一定の遺産が見込まれ、一定の相続人が発生する可能性がある場合で、法定相続分通りの分け方ではなく、誰にどの遺産をどのように分けるのか決めたい場合には遺言書を作成することが必要です。

例えば、夫である自分が亡くなり、夫婦の間に子どもはおらず、相続人としては妻と、夫の兄弟となる場合に、妻のみに全ての遺産を相続させたい場合は、そのような遺言書を作成することで妻に遺産を相続させ、妻のその後の生活を守ることができます。
また、母である自分が亡くなり、夫は既に他界している為、子ども2人(長男と次男)が相続人となっているケースでは、長年の介護をしてくれた長男に遺産を多く分け、次男には一定額を分けたいという場合にも、そのような遺言書を作成することで実現ができます。この場合には、将来の相続で長男と次男の間でトラブルにならないよう、次男には遺留分相当額を分けるようにすることをお勧めします。
さらに、法定相続人ではない人、お世話になった福祉団体などに遺産を引き継がせたい場合は、遺言書が必要です。例えば、いわゆる内縁の妻(事実婚の配偶者)は、法定相続人にはなりませんので、遺言書を書いておかないと、財産を引き継がせることができません。

このように、遺言書の書き方や遺産の評価の仕方には注意点がありますので、遺言書を作成される際には、ぜひ一度ご相談ください。
「相続法はどう変わった?」「どう対応すればいい?」
「相続法が変わった・相続法が変わると聞いた、どう対応すればいいか」というような相談が増えています。今回はこの問題を考えてみます。なお、不動産登記、税制の改正もありますが、その部分は、司法書士、税理士の分野ですので、ここでは触れません。

▶ 相続法のどこが変わったか、どこが変わるか
相続法の分野は(も)このところ法改正が進んでいます。
既に変わったところとしては、(代表的なところでは)、配偶者居住権の新設、遺留分制度の改正、遺産分割協議における主張制限、所在不明者がいる場合の相続財産管理制度、土地の国庫帰属です。法改正が終わって今後施行されるのは、相続登記と住所変更登記の義務化です。
▶ 自筆証書遺言の改正
平成31年1月13日以降に作成される自筆証書遺言では財産目録を自筆する必要がなくなりました。遺言書保管制度も令和2年7月10日から始まっています。

▶ 遺留分制度の改正
令和元年7月1日以降の死亡に適用されます(遺言書の作成日ではありません)。改正前は、個々の遺産について遺留分の限度で権利が移転する(例えば、遺留分が8分の1だとすると、不動産の持分が8分の1移転し、共有になる)とされていましたが、改正後は、遺留分侵害額の限度で金銭請求できる(前例では、不動産の価値の8分の1を金銭請求する)となりました。「不動産を全部相続させる」こと自体は遺留分の請求があっても変更されないということです。

▶ 配偶者居住権
夫と妻が居住していた夫名義の建物について、夫が死亡した場合に妻に(一時または終身)居住権を認める制度です。令和2年4月1日以降の死亡に適用されます。
この制度については、配偶者居住権が発生した場合の建物評価額などいくつかの問題がありますが、ここでは省略します。
▶ 遺産分割協議における主張制限
相続開始(被相続人の死亡)から10年を経過すると、遺産分割にあたって、特別受益(ある相続人は被相続人から贈与を受けていたなど)、寄与分(ある相続人が被相続人の遺産の増加、維持に特別の寄与をした)ことを主張することができなくなります。これは、令和5年4月1日から施行されています。この改正は過去の相続にもさかのぼって適用されるので注意が必要です(経過措置あり)。
遺産分割協議自体に期限はありませんが、10年経過により、上記のような主張ができなくなりますので、遺産分割協議を促進する効果が期待されています。
まだ、施行直後で実例はこれからですが、往々にして、実家の土地家屋が父の所有、父が死亡した後、相続登記をせず、母が死亡してから子どもの間で遺産相続の話し合いを始める、ということがあります。父が死亡してから10年を経過していると、父の遺産相続については、特別受益、寄与分の主張ができなくなるというようなことが起きそうです。
▶ 所在不明者がいる場合の相続財産管理制度
これも令和5年4月1日から施行されています。従来の相続財産管理制度は、「人単位」となっており、その人の相続財産全体について管理することになっていましたが、今回の改正で「物単位」で財産管理人を選任することができるようになりました。ある不動産について相続人の所在が不明なために売却などができないというような場合に、その不動産についての管理人を選任することができるようになったのです。
▶ 土地の国庫帰属
令和5年4月27日から施行されています。一定の条件を満たす場合に、土地の所有権を国に帰属させる制度です。建物は含まれないので要注意。

▶ 最後に
いくつか説明しましたが、結構複雑です。弁護士も、これまでの常識が通用しないので、事案ごとに調査しながら間違いない対応に努めています。お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
特別受益の持戻し免除の意思表示の推定について

【事案】のAさんは、Bさんの老後生活の安定を考えて今2人で住んでいる自宅をBさんに贈与した後、しばらくして亡くなりました。
Aさんの相続人はBさんとCさんになりますが、遺産分割するときに、Aさんが生前Bさんに贈与した自宅はどのように扱われるのでしょうか。
■ 特別受益の持ち戻しとは? ■
AさんからBさんへの自宅の贈与のような、被相続人の生前贈与や遺贈を『特別受益』といい、遺産分割のときには贈与や遺贈された金額を相続財産の中に計算上加えて、具体的な相続分を決めることになります(民法903条第1項)。このことを『特別受益の持戻し』といいます。
(1)「特別受益の持ち戻し」をする場合
BさんとCさんが法定相続分どおり(それぞれ2分の1ずつ)遺産分割を行うことになると、自宅分の金額を相続財産に加えた上で計算し、すでに自宅を貰っているため自宅分の金額を差し引くことになりますので、Bさんは預貯金500万円をもらうことになります。
【計算】 (20,000,000円+30,000,000円)÷2-20,000,000円=5,000,000円

(2)「特別受益の持ち戻し」をしない場合
被相続人は、『特別受益の持戻し』をしないという意思表示(これを『持戻し免除の意思表示』といいます。)ができるので(民法903条第3項)、Aさんが自宅の金額を含めずに相続分を決めるといった意思表示をしていれば、Bさんは預貯金から1500万円ももらえることになります。
【計算】 30,000,000円÷2=15,000,000円

以上のとおり、Aさんが持戻し免除の意思表示をしていなかったかどうかで、Bさんが使えるお金が1000万円も違ってしまいます。
今回の相続法の改正では、この『特別受益の持戻し免除の意思表示』があったものとする推定規定(民法903条第4項)が定められました。
Aさんのように、夫婦の一方が他方に対して居住用不動産の贈与などをする場合、通常それまでの長年の貢献に報いると共に、その老後の生活を保障する趣旨で行われるものと考えられることなどの事情が考慮され、一定の場合に『特別受益の持戻し』が行われる場合の原則と例外が逆転することになりました。
では、どのような場合に推定規定が適用されるのでしょうか。
■ 『特別受益の持ち戻し免除の意思表示』の推定規定が適用されるケース ■
それは、次の2つの要件を満たしたときとなります。
(1)婚姻期間が20年以上の夫婦であること
問題となる贈与や遺贈が行われた時点で、法律上の婚姻期間が20年以上となっている必要があります。
同じ人と結婚と離婚を繰り返している場合には通算で20年以上となっていれば大丈夫ですが、事実婚の期間を含めることはできません。
また、たとえば、贈与が行われたのが婚姻期間10年目だった場合、相続開始時点で婚姻期間が20年以上経過していても要件を充たしません。
(2)居住用不動産の贈与又は遺贈がされたこと
対象となる贈与等の目的物は、自宅といった居住用不動産になります。
贈与などが行われた時点で居住用になっている必要がありますが、近い将来居住用にする目的があったと認められる場合には、要件を充たすと判断される可能性があります。
また、居宅兼店舗の不動産を贈与などした場合、その不動産の構造や形態、被相続人の遺言の趣旨等によって判断されます。
推定規定が適用されるかどうかは実質をみて判断されることがあり、一概にこうだと言い切れるものではありません。ご自身の場合に適用されるのか、迷った場合には、弁護士にご相談いただけたらと思います。
特別寄与料について(相続法改正)
~相続人以外の者の貢献を配慮するための方策~

但し、気をつけなければならないのは期限があることです。
遺留分制度が変わりました。
平成30年相続法改正で遺留分制度が変わりました。

人は、本来自由に自分の財産を処分することができますので、生前の贈与や遺言状の作成によって、法で定められた相続人と異なる人に自分の財産を相続させることも、特定の相続人に全財産を相続させることもできるはずです。
しかし、民法は、一定の範囲の相続人(配偶者、子、直系尊属)に遺留分を認めて、被相続人による 自由な財産の処分(贈与・遺贈)に一定の制限をしています。
相続制度が、遺族の生活保障や、潜在的持分の精算という機能を有していることを考慮し、また、近親者の相続期待権を保護しているのです(遺留分を主張しないこともまた自由です)。
改正前、遺留分権利者は、遺贈を受けた人や贈与を受けた人に対し、「遺留分減殺請求権」を行使することができましたが、現物返還の原則が基本とされ、また、遺留分権利者の方で減殺の対象となる財産を選ぶことができず、遺産全体について価格の割合に応じて減殺すべきとしていたため、遺留分義務者が価格弁償を選択しない限り、不動産が共有となり、さらに共有物分割の手続きが必要となって、紛争の解決が長期化しがちでした。
改正によって、遺留分権利者は、「遺留分侵害額請求権」をもつことになり、侵害額の支払を請求する方式に変わりました。以前より、格段に請求が容易になったのです。令和元年7月1日以降にお亡くなりになられた方から適用があります。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年で時効により消滅します。相続開始の時から10年の経過によっても消滅します。
ご相談の際には、遺留分侵害額請求権を行使できる期間にご注意頂き、お早めにご相談ください。